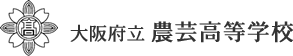2024年12月27日(金)農芸高校の最寄り駅南海電鉄萩原天神駅近くの萩原神社へ門松の設置へ行きました。
昨年よりご縁があり、設置の機会をいただき、今年も継続して門松設置の機会をいただきました。
昨年設置の様子
萩原神社沿革
当神社所有の文書では元禄年間(約300年前)の寺社改帳が現存する一番古い古文書です。それより古い記録は存在しないが、境内から発掘される平安時代の古瓦などから推察すれば伝えの如く、神仏混合時代には僧行基(奈良時代)の開基したと云う「萩原寺」が 神仏の聖地として栄え、数院の塔頭を有し「萩原山」の山号で称され広い信仰を集めていたことがうかが える。尚 現在も原寺の妙覚寺の山号は萩原山を冠している。
又 鎮座地の「原寺」の地名も萩原寺の萩をいつしか略したものと思われる。尚 南北朝には戦火にあい、その後 妙覚寺、正福寺、釈迦院、地蔵院、観音院を近村に遷したと伝えられる。
明治末期には近在より七社が 当社に合祀され、現在は広大な氏子区域を有す。また日置西村の大庄屋日置氏(吉村家)の氏神は、当社に合祀されている天櫛玉命であるが、日置氏は極めて天神信仰が篤かった事跡が顕著である。
萩原神社HPより引用
住宅街の中にひっそりとたたずむ萩原神社の社叢は堺市指定保存樹木にも指定されている樹高11m・周囲2.5mのクスの巨木をはじめ萩原神社一体の植生を残す貴重な森になっています。
設置当日は風の強い日となりましたが、社叢に守られ設置作業を行うことができました。
- 荷物の搬入
- ビールケースの上に器を置きます
- タケの準備
- 器に竹を立てます
- 縦方向と横方向にブレがないように芯を見極めます
- 地域の住民の方も作業を見られて完成を楽しみにしてくれました。
- 土嚢袋で竹を固定します
- 主役となるマツは萩原神社の境内より松迎(切り出し)を行いました。
- 選別した松をさしていきます。
- 境内の社叢からいただいたナンテンをさします
- 角度や高さを確認していきます
- ビールケースの上に設置することで高さを出し、立体的な仕上がりにします
- 農芸高校で栽培したハボタンを並べます
- 向かって左側が赤色
- 向かって右側が白色
- ビールケースが見えないように飾り付けます
- 後ろ側まで仕上がりを確認します
- 謹製の看板の周囲も植栽をします。
- 白い葉ボタンでへび年にちなんだ白いへびの尾をイメージしてあしらいました
- 完成全景
- 社殿と門松はどの角度から撮影しても見栄えがします
- 後方に伸びたへびの尾
- 謹製の看板は斑入りのバランで高さを出し、足元をハボタンや下草で仕上げました
- 設置前
- 設置後
- 教職員と3年生の生徒で仕上げました
昨年に引き続き、2回目の設置で少人数の中限られた時間で昨年よりも立体的でまとまりのある門松を設置することができました。
参加した生徒は昨年設置を経験した生徒だったこともあり、慣れた手つきで植栽を仕上げ、卒業を前に立派な門松を納めることができました。
来年の干支にちなんだハボタンをふんだんに使ったヘビー級門松となりました。
1月7日までの設置となります。
お近くにお立ち寄りの際はぜひご覧ください。